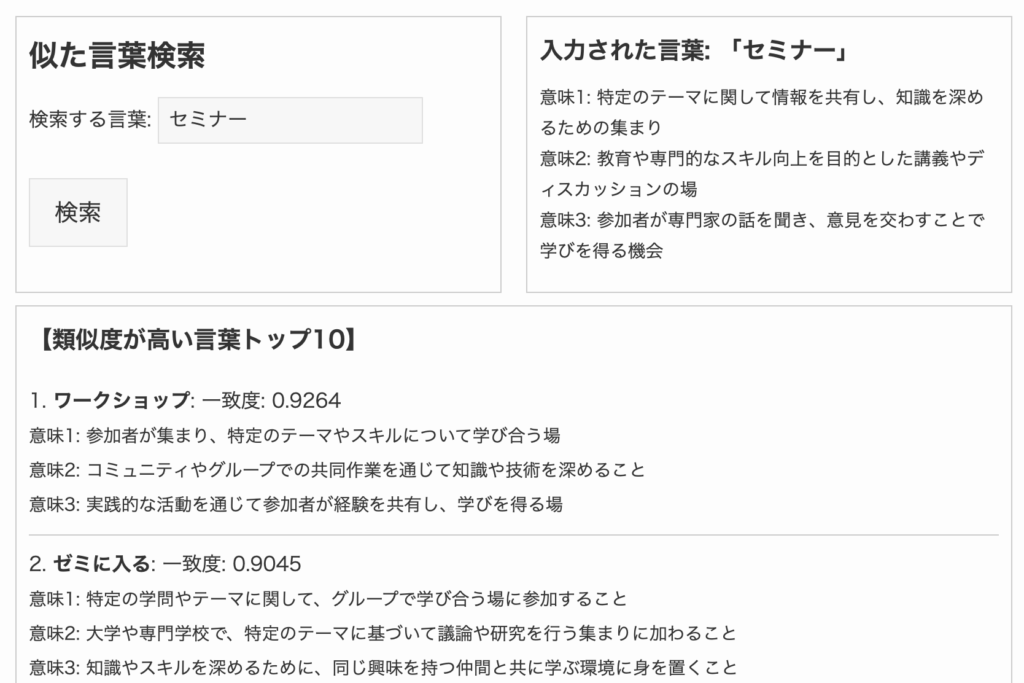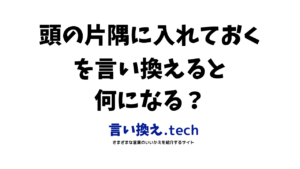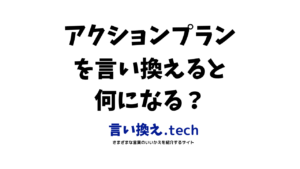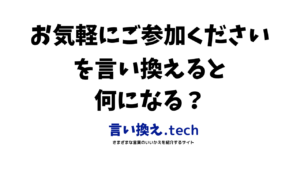本記事では、新しいものに変えるの言い換え語・同義語(類義語)を解説します。
- ビジネスで使えるきっちりした類語
- 友達同士でカジュアルで使える類語
に分けていくつかのアイデアをまとめました。
また、カタカナ・英語でかっこよく言い換えたい場合のワードもいくつか紹介します。
実際に使われているワードばかりです。ぜひ参考にしてください。
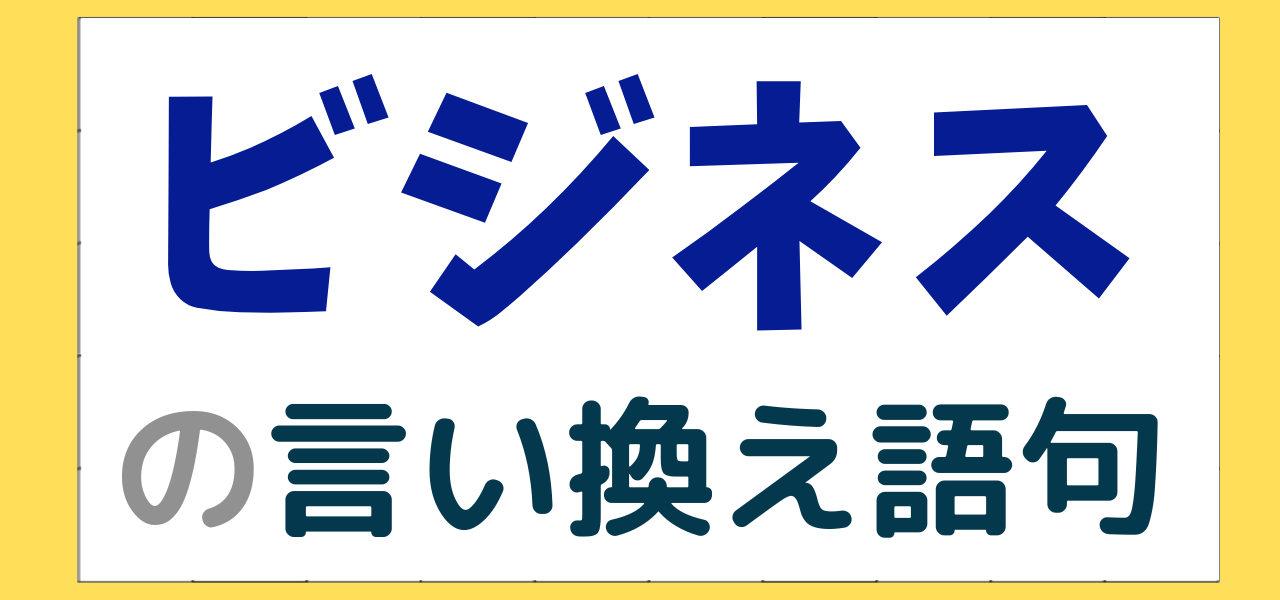 →ビジネスの言い換えを見る | 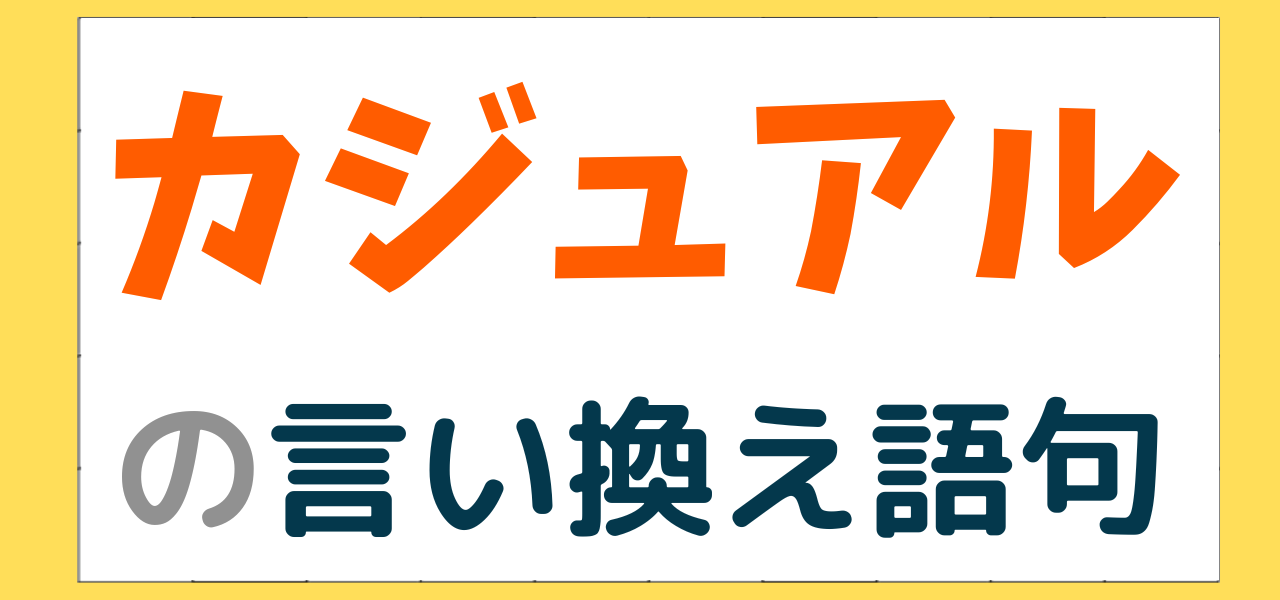 →カジュアルの言い換えを見る | 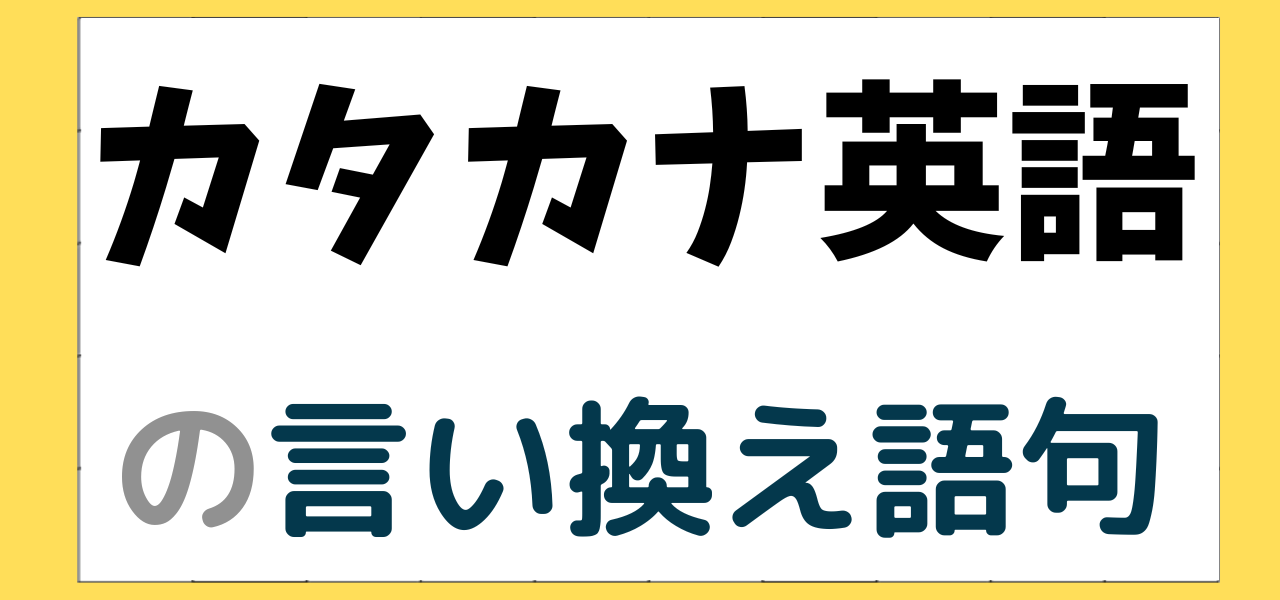 →英語・カタカナの言い換えを見る |
新しいものに変えるとは? そもそもどんな意味か?
まずは新しいものに変えるとはどんな意味なのかをおさらいします。
すでに意味をご存知の方は、次の項目まで飛ばしていただき大丈夫です。
意味
まず意味は以下のとおりです。
—
既存の方法や考え方から脱却して新たな選択肢を持つこと—
革新を通じてより良い結果を得ること意味を全て見る
- 変化を受け入れ、適応することによって成長すること
- 既存の枠組みを壊して新たな価値を創造すること
例文
つづいて、新しいものに変えるを用いた例文を紹介します。
私たちは新しい技術に変えることで、効率を大幅に向上させました。
古いシステムを新しいものに変えることで、業務がスムーズになりました。
例文を全て見る
- 新しいアプローチに変えることで、顧客満足度が向上しました。
- 従来の方法を新しいものに変えることが、成功の鍵でした。
- 市場のニーズに合わせて、製品を新しいものに変える必要があります。
注意点(違和感のある、または失礼な使い方)
この言葉を使ううえでの注意点は以下のとおりです。違和感のある使い方にならぬよう注意しましょう。
—
この表現は、改善や進化を示しますが、急激な変化に対する不安を引き起こすこともあるため、慎重に使う必要があります。ビジネスで使える丁寧な新しいものに変えるの言い換え語のおすすめ
ビジネスで使えるフォーマルな言い換え語を紹介します。
それぞれ見ていきます。
イノベーション
まずは、イノベーションです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
アップデート
2つ目は、アップデートです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
リニューアル
3つ目は、リニューアルです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
改革
4つ目は、改革です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
変革
5つ目は、変革です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
刷新
6つ目は、刷新です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
進化
7つ目は、進化です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
適応
8つ目は、適応です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
改善
9つ目は、改善です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
最適化
10個目は最適化です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
新しいものに変えるのカジュアルな言い換え語のおすすめ
友達同士で使えるようなカジュアルな言い換え語のおすすめを紹介します。
チェンジ
まずは、チェンジです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
変わり身
カジュアルの2つ目は、変わり身です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
バージョンアップ
つづいて、バージョンアップです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
リフレッシュ
4つ目は、リフレッシュです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
パッチ
5つ目は、パッチです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
アジャスト
6つ目は、アジャストです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
トランスフォーム
7つ目は、トランスフォームです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
シフト
8つ目は、シフトです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
アップ
9つ目は、アップです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
リボン
10個目は、リボンです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
新しいものに変えるの横文字・カタカナ英語の言い換え語のおすすめ
最後は横文字・カタカナ英語での言い換え語を紹介します。
こちらはリストのみとなります。
- チェンジ
- リニューアル
- アップデート
- Change(変化)
- Renew(更新)
- Update(改訂)
かっこよく表現したい際、参考にしてください。
まとめ
以上が新しいものに変えるの言い換え語のおすすめでした。
さまざまな言葉があることがわかりますね。
基本的な意味は同じでも微妙にニュアンスが違ったりもするため、TPOに合わせて言い換え語を使い分けていきましょう。
振り返り用リンク↓