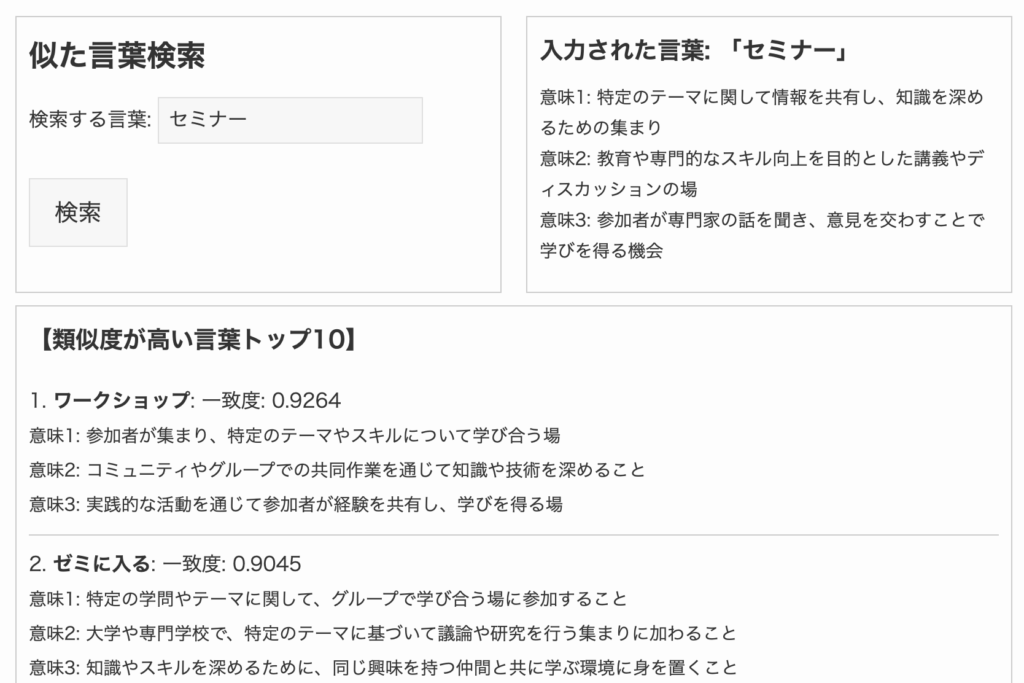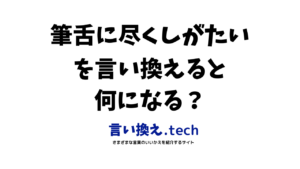本記事では、古いやり方の言い換え語・同義語(類義語)を解説します。
- ビジネスで使えるきっちりした類語
- 友達同士でカジュアルで使える類語
に分けていくつかのアイデアをまとめました。
また、カタカナ・英語でかっこよく言い換えたい場合のワードもいくつか紹介します。
実際に使われているワードばかりです。ぜひ参考にしてください。
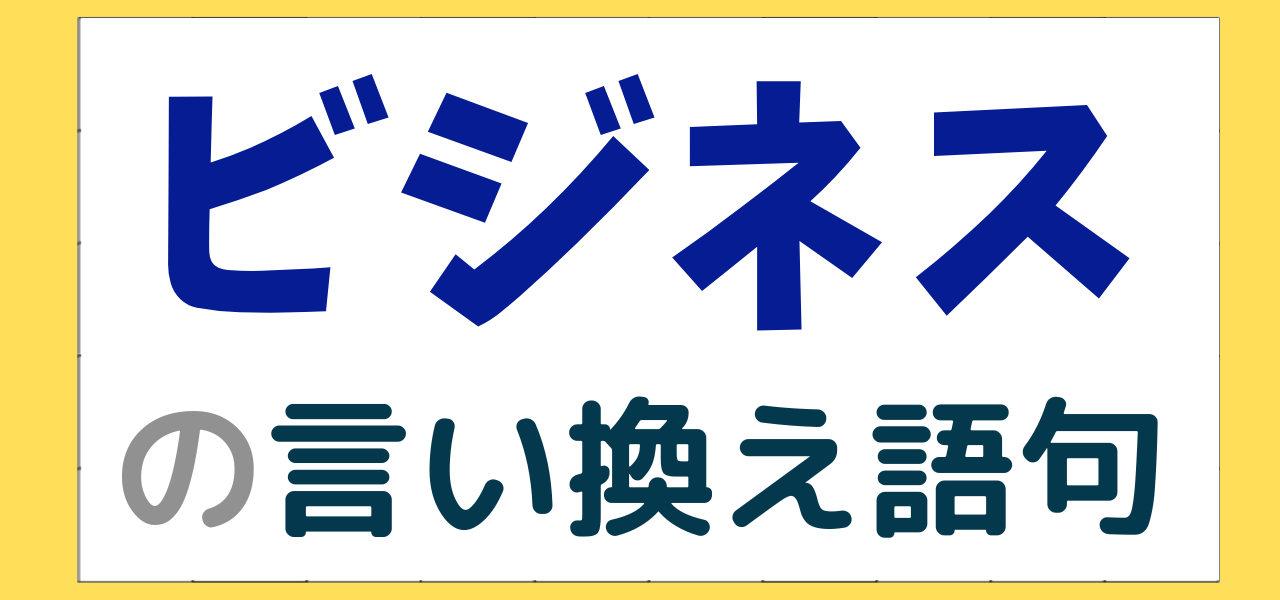 →ビジネスの言い換えを見る | 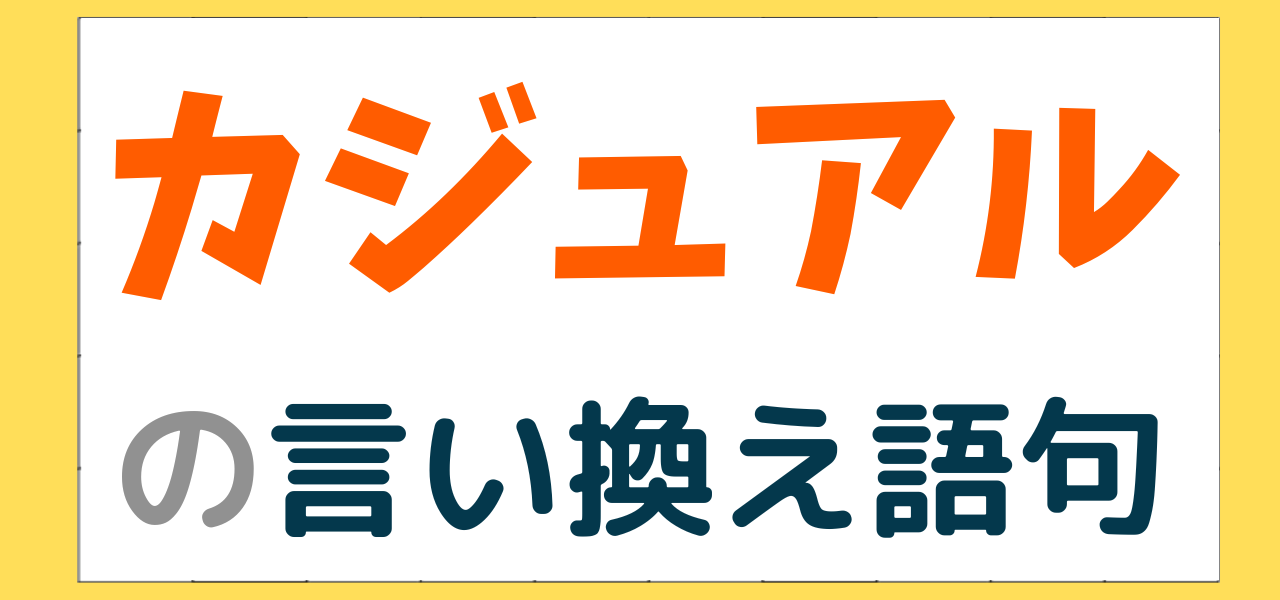 →カジュアルの言い換えを見る | 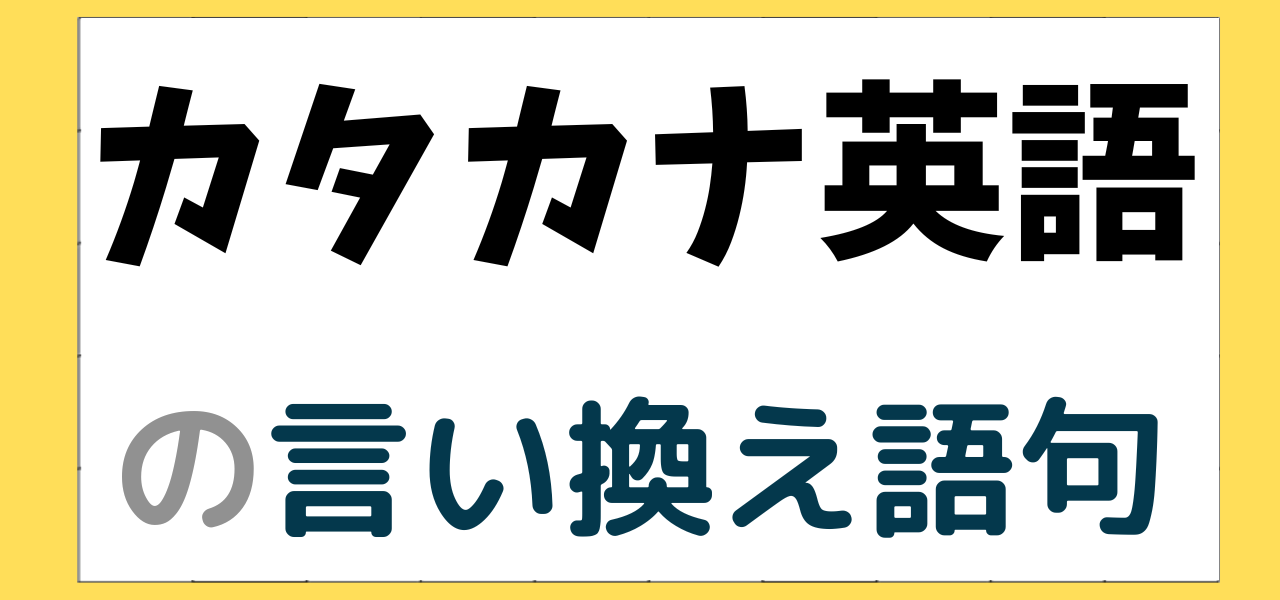 →英語・カタカナの言い換えを見る |
古いやり方とは? そもそもどんな意味か?
まずは古いやり方とはどんな意味なのかをおさらいします。
すでに意味をご存知の方は、次の項目まで飛ばしていただき大丈夫です。
意味
まず意味は以下のとおりです。
—
伝統的なやり方を踏襲すること—
新しい技術や手法を使わずに行うこと意味を全て見る
- 時代遅れの手法を維持すること
- 効率が悪いが、慣れ親しんだ方法で行うこと
例文
つづいて、古いやり方を用いた例文を紹介します。
彼のビジネスは古いやり方に固執している。
古いやり方で運営されている店は、時代に取り残されている。
例文を全て見る
- 新しいアイデアを取り入れず、古いやり方を続けている。
- 彼女は古いやり方を守り続けて、成功している。
- 古いやり方にこだわることは、リスクを伴う。
注意点(違和感のある、または失礼な使い方)
この言葉を使ううえでの注意点は以下のとおりです。違和感のある使い方にならぬよう注意しましょう。
—
この表現は、保守的なアプローチを示しますが、時には新しいアイデアを拒むという否定的なニュアンスを含むことがあるため、文脈によって使い分けることが重要です。ビジネスで使える丁寧な古いやり方の言い換え語のおすすめ
ビジネスで使えるフォーマルな言い換え語を紹介します。
それぞれ見ていきます。
伝統的手法
まずは、伝統的手法です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
従来のアプローチ
2つ目は、従来のアプローチです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
保守的手法
3つ目は、保守的手法です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
古典的手法
4つ目は、古典的手法です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
従来型
5つ目は、従来型です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
旧態依然
6つ目は、旧態依然です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
伝統的アプローチ
7つ目は、伝統的アプローチです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
維持型
8つ目は、維持型です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
非革新型
9つ目は、非革新型です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
旧式手法
10個目は旧式手法です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
古いやり方のカジュアルな言い換え語のおすすめ
友達同士で使えるようなカジュアルな言い換え語のおすすめを紹介します。
昔ながら
まずは、昔ながらです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
アナログ
カジュアルの2つ目は、アナログです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
レトロ
つづいて、レトロです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
昔のやり方
4つ目は、昔のやり方です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
保守的スタイル
5つ目は、保守的スタイルです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
昔の流儀
6つ目は、昔の流儀です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
手作り
7つ目は、手作りです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
古典的スタイル
8つ目は、古典的スタイルです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
スローテクノロジー
9つ目は、スローテクノロジーです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
ノスタルジック
10個目は、ノスタルジックです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
古いやり方の横文字・カタカナ英語の言い換え語のおすすめ
最後は横文字・カタカナ英語での言い換え語を紹介します。
こちらはリストのみとなります。
- レトロ
- アナログ
- クラシック
- Traditional methods(伝統的手法)
- Conventional approach(従来のアプローチ)
- Old-fashioned techniques(古風な技術)
かっこよく表現したい際、参考にしてください。
まとめ
以上が古いやり方の言い換え語のおすすめでした。
さまざまな言葉があることがわかりますね。
基本的な意味は同じでも微妙にニュアンスが違ったりもするため、TPOに合わせて言い換え語を使い分けていきましょう。
振り返り用リンク↓