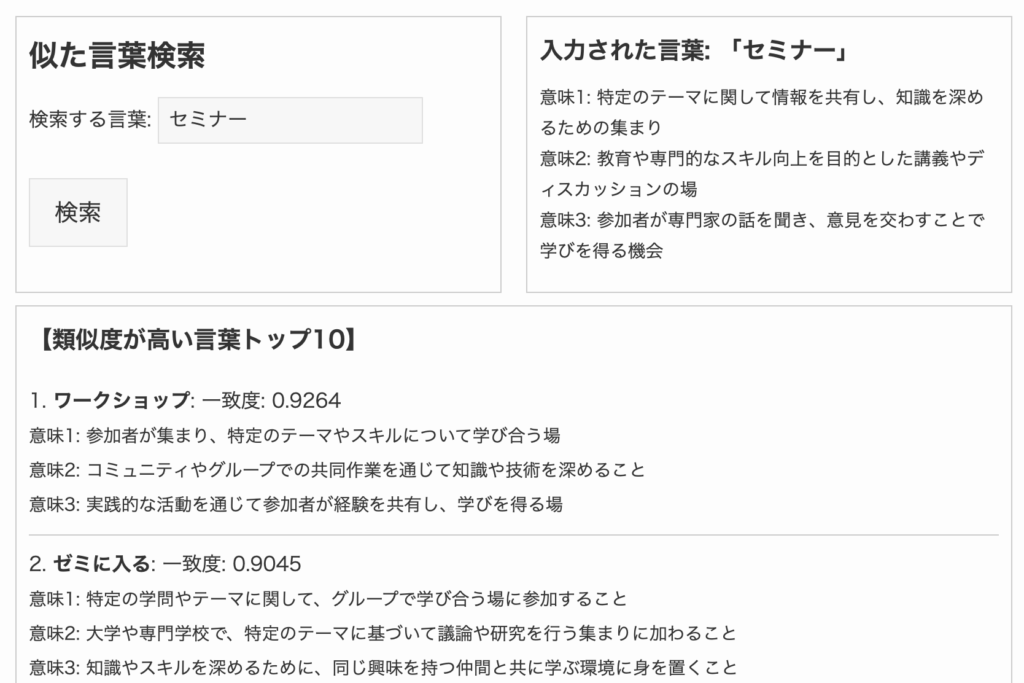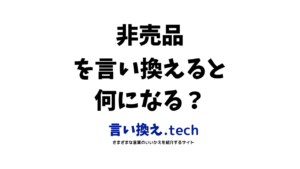本記事では、ベタ打ちの言い換え語・同義語(類義語)を解説します。
- ビジネスで使えるきっちりした類語
- 友達同士でカジュアルで使える類語
に分けていくつかのアイデアをまとめました。
また、カタカナ・英語でかっこよく言い換えたい場合のワードもいくつか紹介します。
実際に使われているワードばかりです。ぜひ参考にしてください。
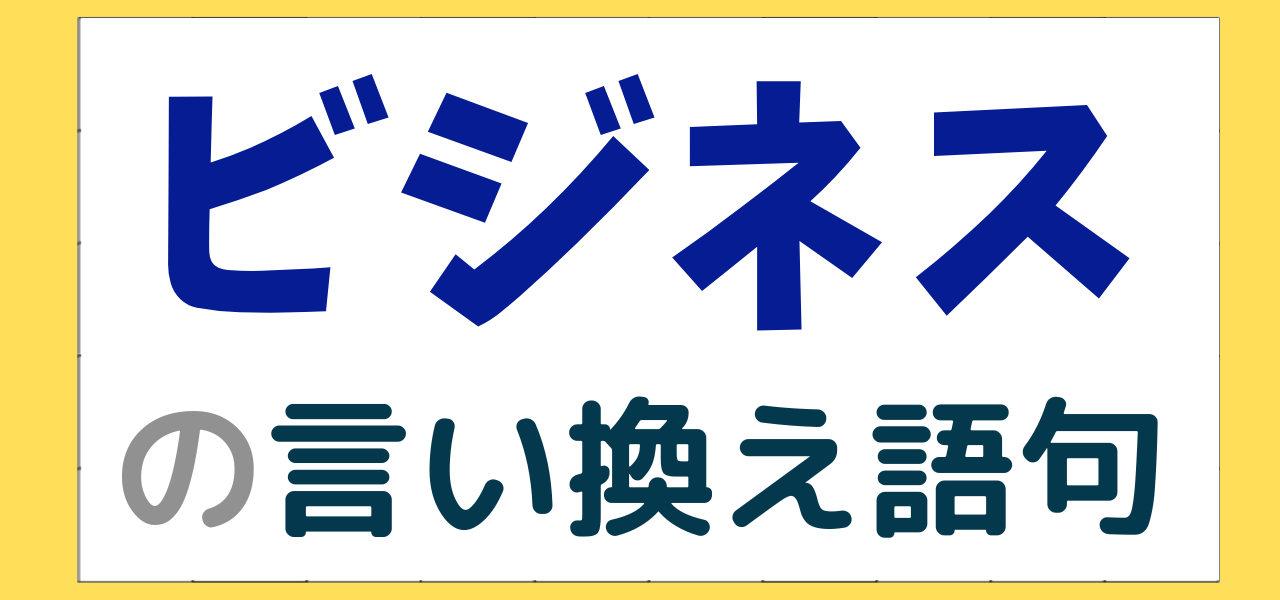 →ビジネスの言い換えを見る | 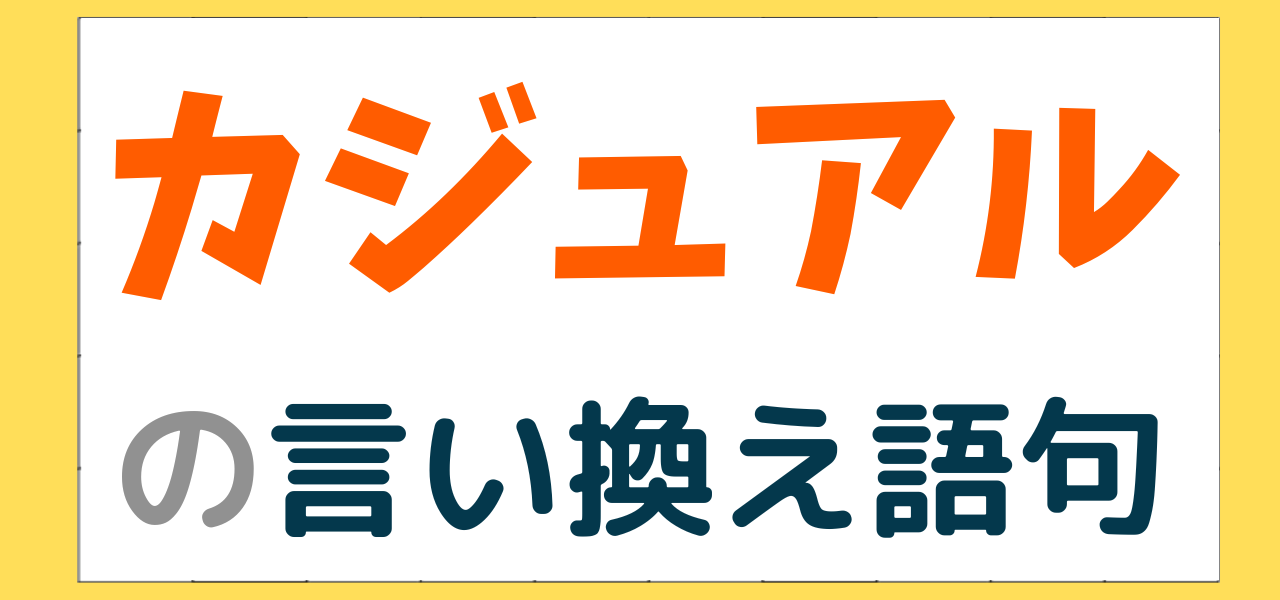 →カジュアルの言い換えを見る | 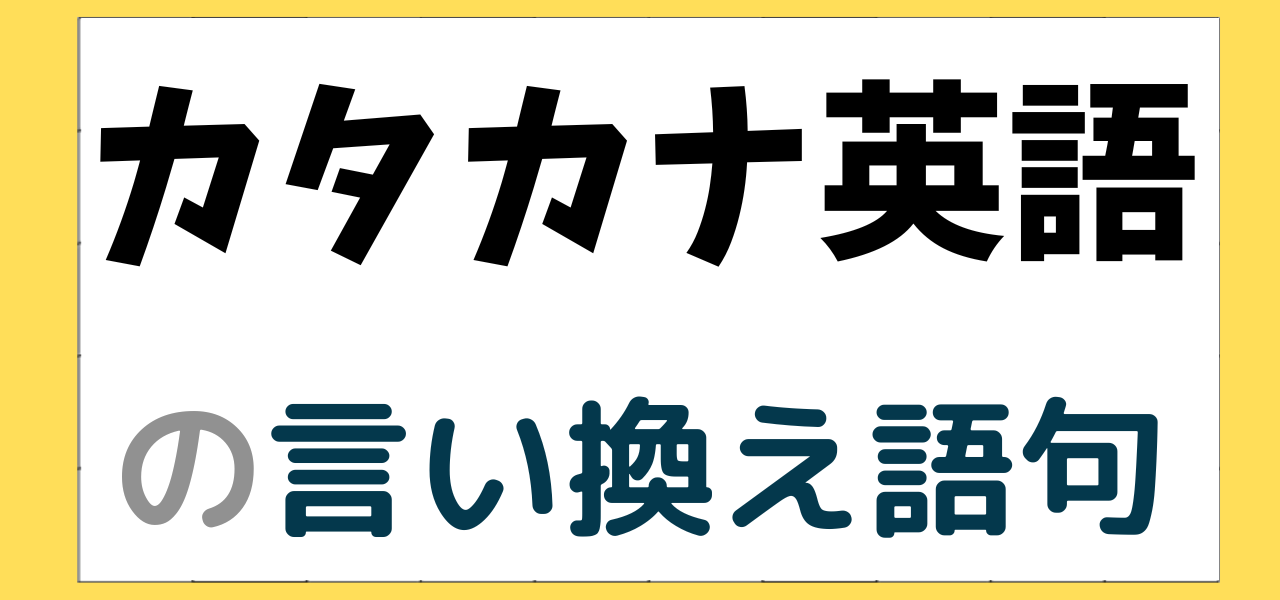 →英語・カタカナの言い換えを見る |
ベタ打ちとは? そもそもどんな意味か?
まずはベタ打ちとはどんな意味なのかをおさらいします。
すでに意味をご存知の方は、次の項目まで飛ばしていただき大丈夫です。
意味
まず意味は以下のとおりです。
—
データやテキストを、特別な装飾や編集なしで入力すること—
入力した内容がそのまま表示されること意味を全て見る
- 簡素な形で情報を提示すること
- 特に装飾やフォーマットを加えずに情報を提供すること
例文
つづいて、ベタ打ちを用いた例文を紹介します。
この文書はベタ打ちで作成されている。
彼のメッセージはベタ打ちで、特に装飾がない。
例文を全て見る
- レポートはベタ打ちで提出されたため、見やすい。
- 彼女はベタ打ちで情報を共有し、すぐに理解できた。
- このデータはベタ打ちで、編集の必要がない。
注意点(違和感のある、または失礼な使い方)
この言葉を使ううえでの注意点は以下のとおりです。違和感のある使い方にならぬよう注意しましょう。
—
この表現は、特にフォーマットを重視しない場合に便利ですが、ビジュアルが求められる場面では適さないことがあります。ビジネスで使える丁寧なベタ打ちの言い換え語のおすすめ
ビジネスで使えるフォーマルな言い換え語を紹介します。
それぞれ見ていきます。
シンプルな入力
まずは、シンプルな入力です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
プレーンテキスト
2つ目は、プレーンテキストです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
基本情報
3つ目は、基本情報です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
ノンスタイル入力
4つ目は、ノンスタイル入力です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
直接入力
5つ目は、直接入力です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
原文
6つ目は、原文です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
ベーシックデータ
7つ目は、ベーシックデータです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
フォーマットなし
8つ目は、フォーマットなしです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
ストレートな入力
9つ目は、ストレートな入力です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
クリーンなテキスト
10個目はクリーンなテキストです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
ベタ打ちのカジュアルな言い換え語のおすすめ
友達同士で使えるようなカジュアルな言い換え語のおすすめを紹介します。
そのまんま打ち
まずは、そのまんま打ちです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
ガチ打ち
カジュアルの2つ目は、ガチ打ちです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
直打ち
つづいて、直打ちです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
サクッと入力
4つ目は、サクッと入力です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
無編集
5つ目は、無編集です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
ザックリ打ち
6つ目は、ザックリ打ちです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
シンプル打ち
7つ目は、シンプル打ちです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
ストレート打ち
8つ目は、ストレート打ちです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
そのまま流し込み
9つ目は、そのまま流し込みです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
ダイレクト打ち
10個目は、ダイレクト打ちです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
ベタ打ちの横文字・カタカナ英語の言い換え語のおすすめ
最後は横文字・カタカナ英語での言い換え語を紹介します。
こちらはリストのみとなります。
- プレーン入力
- ノンスタイル
- シンプルテキスト
- Plain input(プレーンな入力)
- Direct input(直接入力)
- Unformatted text(フォーマットなしのテキスト)
かっこよく表現したい際、参考にしてください。
まとめ
以上がベタ打ちの言い換え語のおすすめでした。
さまざまな言葉があることがわかりますね。
基本的な意味は同じでも微妙にニュアンスが違ったりもするため、TPOに合わせて言い換え語を使い分けていきましょう。
振り返り用リンク↓