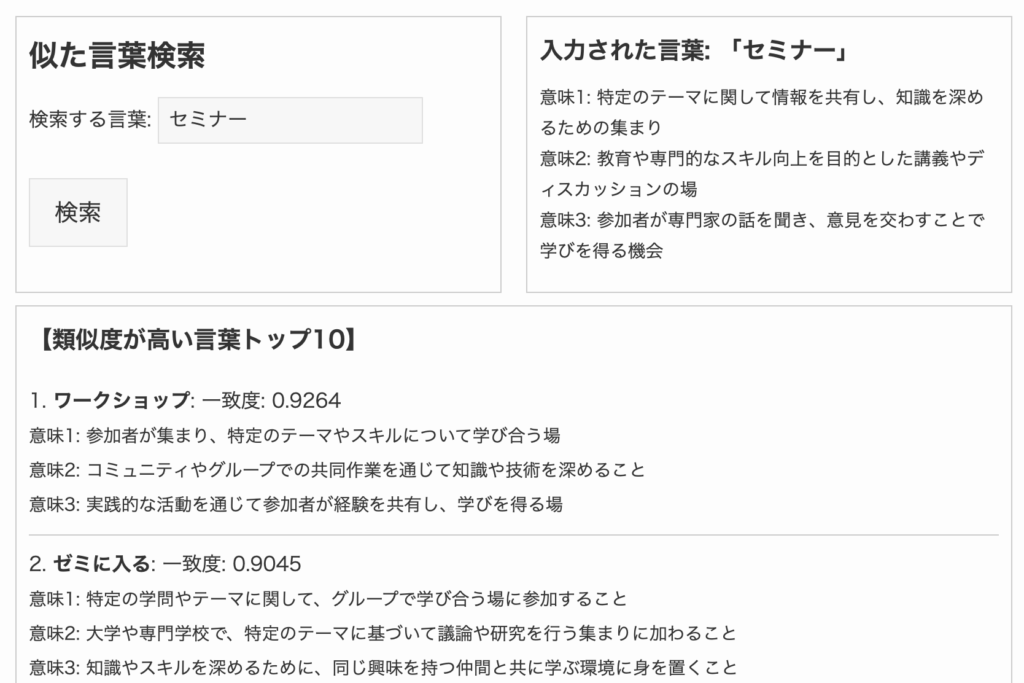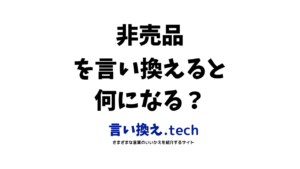本記事では、文武両道の言い換え語・同義語(類義語)を解説します。
- ビジネスで使えるきっちりした類語
- 友達同士でカジュアルで使える類語
に分けていくつかのアイデアをまとめました。
また、カタカナ・英語でかっこよく言い換えたい場合のワードもいくつか紹介します。
実際に使われているワードばかりです。ぜひ参考にしてください。
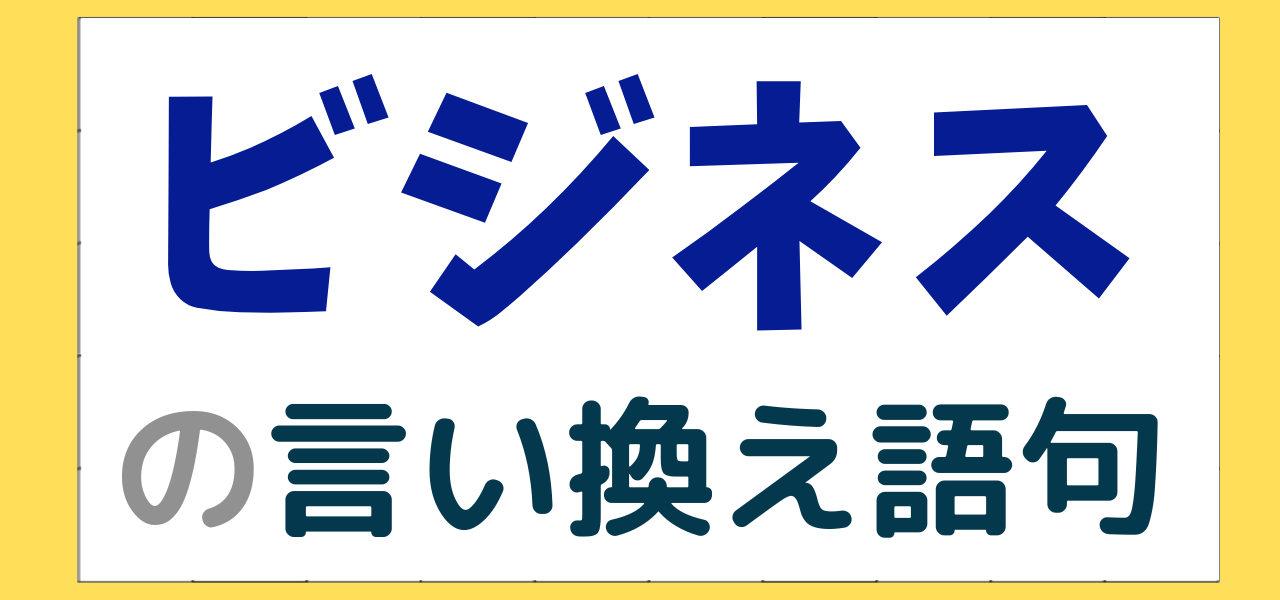 →ビジネスの言い換えを見る | 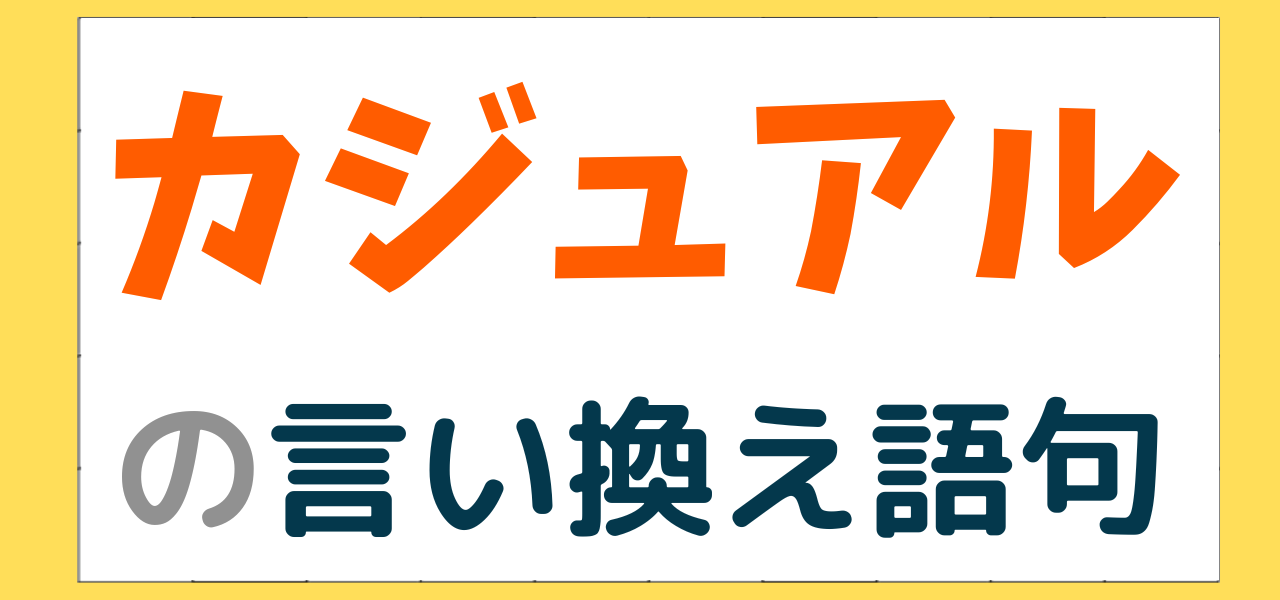 →カジュアルの言い換えを見る | 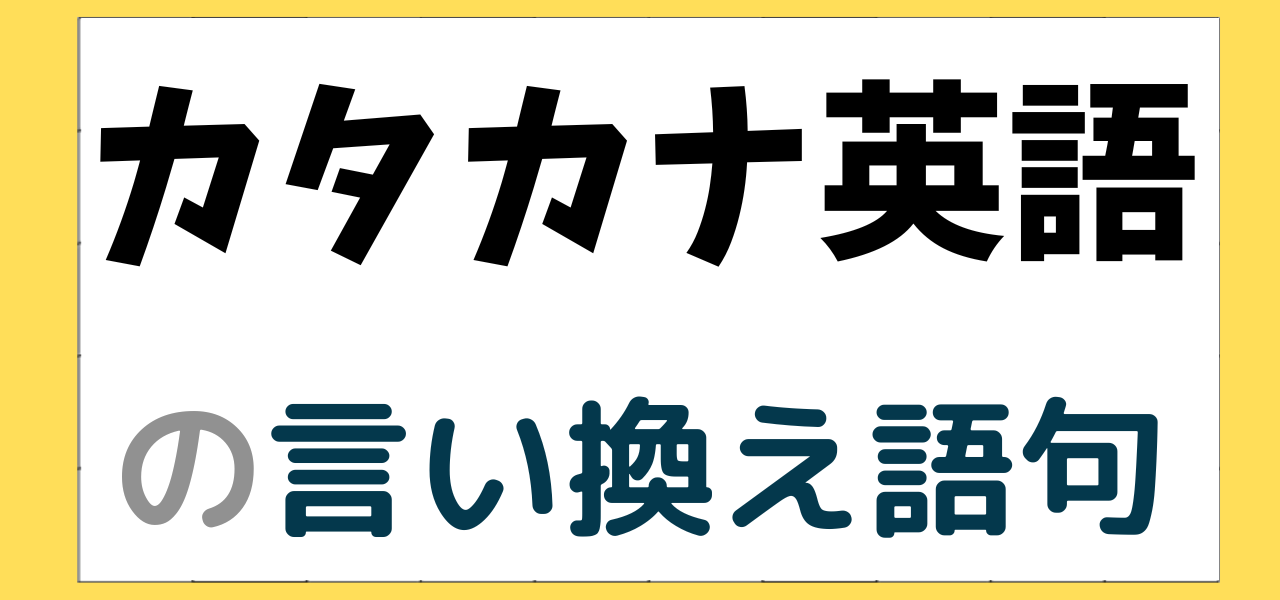 →英語・カタカナの言い換えを見る |
文武両道とは? そもそもどんな意味か?
まずは文武両道とはどんな意味なのかをおさらいします。
すでに意味をご存知の方は、次の項目まで飛ばしていただき大丈夫です。
意味
まず意味は以下のとおりです。
—
学問と武道の両方で優れた能力を持つこと—
精神的な成長と身体的な成長を同時に追求すること意味を全て見る
- 多面的なスキルを持つことで、さまざまな場面で成功すること
- 知識と実践のバランスを取ること
例文
つづいて、文武両道を用いた例文を紹介します。
彼は文武両道を体現した人で、学業もスポーツも優秀だ。
文武両道の精神で、彼女は学問と武道の両方で成果を上げている。
例文を全て見る
- 文武両道を目指すことで、彼は自己成長を遂げた。
- 文武両道の考え方が、彼女のキャリアにプラスの影響を与えている。
- 文武両道を実践することで、彼は多様なスキルを身につけた。
注意点(違和感のある、または失礼な使い方)
この言葉を使ううえでの注意点は以下のとおりです。違和感のある使い方にならぬよう注意しましょう。
—
この用語は、特に教育や自己啓発の場で使われることが多いですが、文脈によっては片方に偏る理解を招く可能性があるため注意が必要です。ビジネスで使える丁寧な文武両道の言い換え語のおすすめ
ビジネスで使えるフォーマルな言い換え語を紹介します。
それぞれ見ていきます。
多才な人材
まずは、多才な人材です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
バランスの取れた専門家
2つ目は、バランスの取れた専門家です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
総合的な能力者
3つ目は、総合的な能力者です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
知識人
4つ目は、知識人です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
実践者
5つ目は、実践者です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
教育者
6つ目は、教育者です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
リーダーシップを持つ人
7つ目は、リーダーシップを持つ人です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
戦略的思考者
8つ目は、戦略的思考者です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
マルチスキル
9つ目は、マルチスキルです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
能力開発者
10個目は能力開発者です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
文武両道のカジュアルな言い換え語のおすすめ
友達同士で使えるようなカジュアルな言い換え語のおすすめを紹介します。
両方できる人
まずは、両方できる人です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
オールラウンダー
カジュアルの2つ目は、オールラウンダーです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
スキルフル
つづいて、スキルフルです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
頭脳明晰
4つ目は、頭脳明晰です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
アクティブライフ
5つ目は、アクティブライフです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
トリプルスレット
6つ目は、トリプルスレットです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
スーパーマン
7つ目は、スーパーマンです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
ハイブリッド
8つ目は、ハイブリッドです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
クリエイティブ
9つ目は、クリエイティブです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
アスリート
10個目は、アスリートです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
文武両道の横文字・カタカナ英語の言い換え語のおすすめ
最後は横文字・カタカナ英語での言い換え語を紹介します。
こちらはリストのみとなります。
- マルチタレント
- マルチスキル
- オールラウンダー
- Versatile(多才な)
- Well-rounded(バランスの取れた)
- Multi-skilled(多様なスキルを持つ)
かっこよく表現したい際、参考にしてください。
まとめ
以上が文武両道の言い換え語のおすすめでした。
さまざまな言葉があることがわかりますね。
基本的な意味は同じでも微妙にニュアンスが違ったりもするため、TPOに合わせて言い換え語を使い分けていきましょう。
振り返り用リンク↓