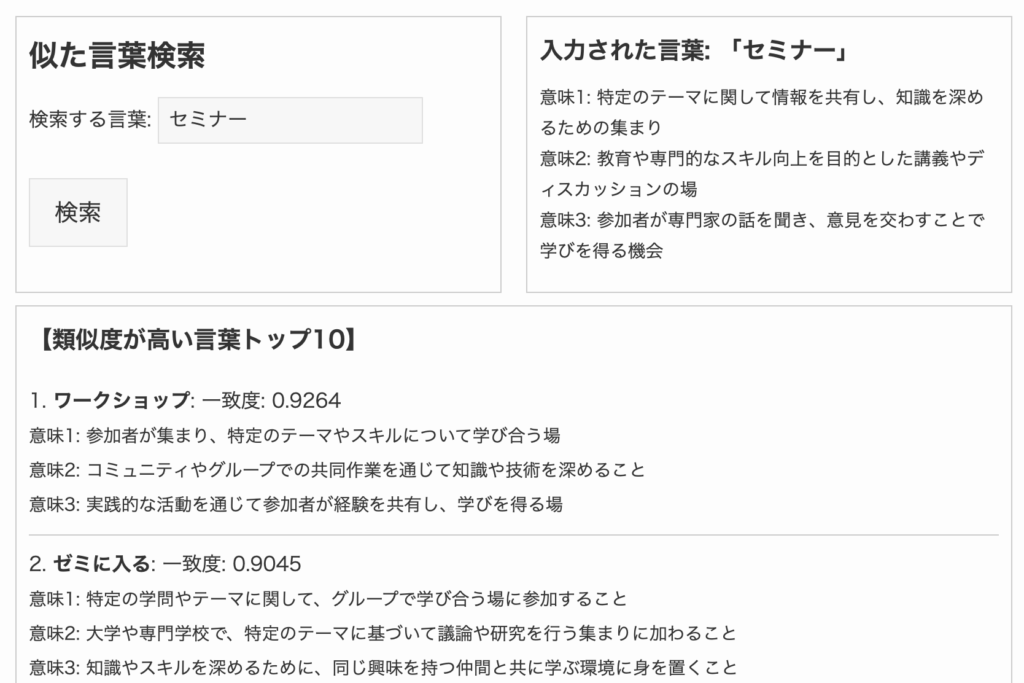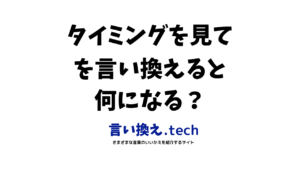本記事では、手戻りの言い換え語・同義語(類義語)を解説します。
- ビジネスで使えるきっちりした類語
- 友達同士でカジュアルで使える類語
に分けていくつかのアイデアをまとめました。
また、カタカナ・英語でかっこよく言い換えたい場合のワードもいくつか紹介します。
実際に使われているワードばかりです。ぜひ参考にしてください。
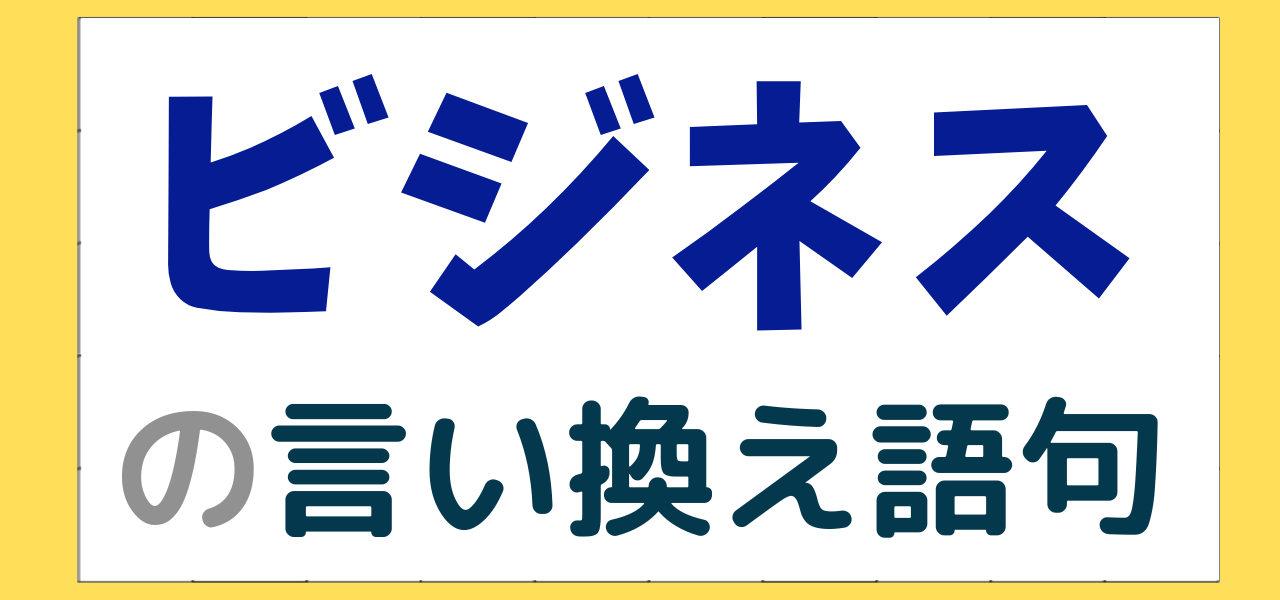 →ビジネスの言い換えを見る | 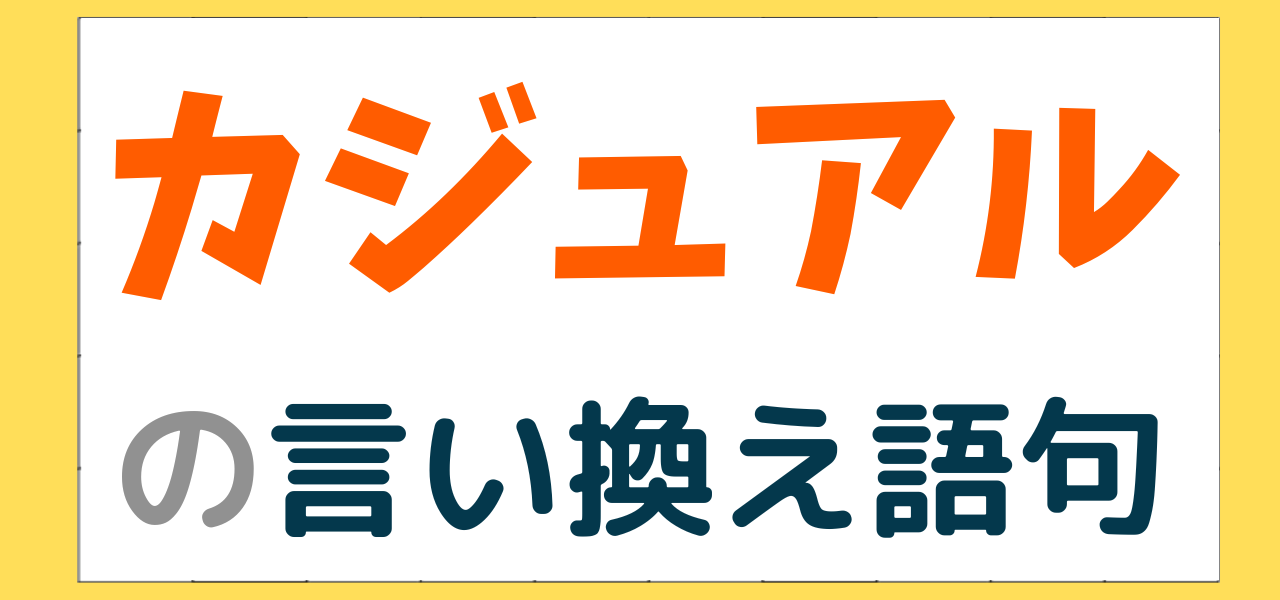 →カジュアルの言い換えを見る | 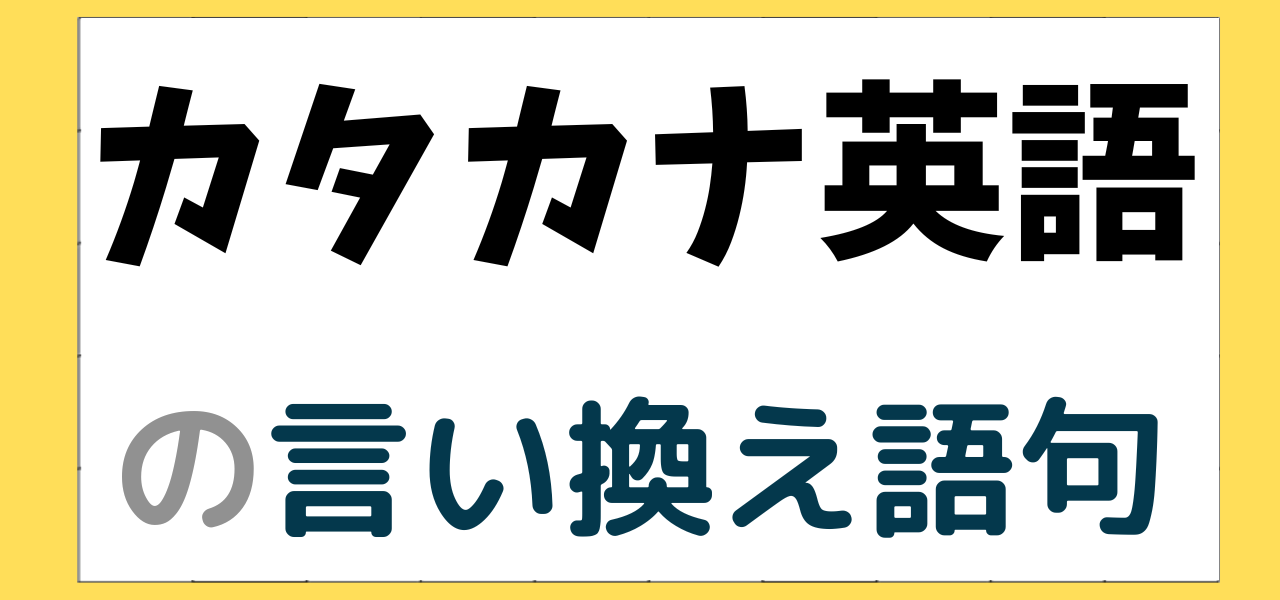 →英語・カタカナの言い換えを見る |
手戻りとは? そもそもどんな意味か?
まずは手戻りとはどんな意味なのかをおさらいします。
すでに意味をご存知の方は、次の項目まで飛ばしていただき大丈夫です。
意味
まず意味は以下のとおりです。
—
計画や作業の進行中に発生した問題に対処するために、過去の作業に戻ること。—
成果物や結果が期待に満たない場合に、以前の状態に戻して修正を行うこと。意味を全て見る
- 作業の進捗を見直し、必要に応じて以前の段階に戻すプロセス。
- プロジェクトの品質を確保するために、過去の作業に立ち返ること。
例文
つづいて、手戻りを用いた例文を紹介します。
彼は手戻りを避けるために、計画を見直した。
プロジェクトの進行中に手戻りが発生し、スケジュールに影響が出た。
例文を全て見る
- 手戻りを減らすために、事前にリスクを洗い出すことが重要だ。
- この作業では手戻りが多く、効率が悪化している。
- 手戻りを防ぐために、確認作業を徹底する必要がある。
注意点(違和感のある、または失礼な使い方)
この言葉を使ううえでの注意点は以下のとおりです。違和感のある使い方にならぬよう注意しましょう。
—
手戻りが発生することは避けたい事態ですが、時には必要な修正を意味する場合もあるため、その旨を明確にすることが重要です。ビジネスで使える丁寧な手戻りの言い換え語のおすすめ
ビジネスで使えるフォーマルな言い換え語を紹介します。
それぞれ見ていきます。
再評価
まずは、再評価です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
修正作業
2つ目は、修正作業です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
プロジェクトの見直し
3つ目は、プロジェクトの見直しです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
品質管理
4つ目は、品質管理です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
リカバリー
5つ目は、リカバリーです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
進捗確認
6つ目は、進捗確認です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
課題解決
7つ目は、課題解決です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
プロセス改善
8つ目は、プロセス改善です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
再作業
9つ目は、再作業です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
改善策
10個目は改善策です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
手戻りのカジュアルな言い換え語のおすすめ
友達同士で使えるようなカジュアルな言い換え語のおすすめを紹介します。
戻り道
まずは、戻り道です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
やり直し
カジュアルの2つ目は、やり直しです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
巻き戻し
つづいて、巻き戻しです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
バックトラック
4つ目は、バックトラックです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
再スタート
5つ目は、再スタートです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
リセット
6つ目は、リセットです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
再チェック
7つ目は、再チェックです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
修正タイム
8つ目は、修正タイムです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
トンネルの出口
9つ目は、トンネルの出口です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
見直しタイム
10個目は、見直しタイムです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
手戻りの横文字・カタカナ英語の言い換え語のおすすめ
最後は横文字・カタカナ英語での言い換え語を紹介します。
こちらはリストのみとなります。
- リバート
- リセット
- リカバリー
- Rollback(巻き戻し)
- Review(見直し)
- Rework(再作業)
かっこよく表現したい際、参考にしてください。
まとめ
以上が手戻りの言い換え語のおすすめでした。
さまざまな言葉があることがわかりますね。
基本的な意味は同じでも微妙にニュアンスが違ったりもするため、TPOに合わせて言い換え語を使い分けていきましょう。
振り返り用リンク↓