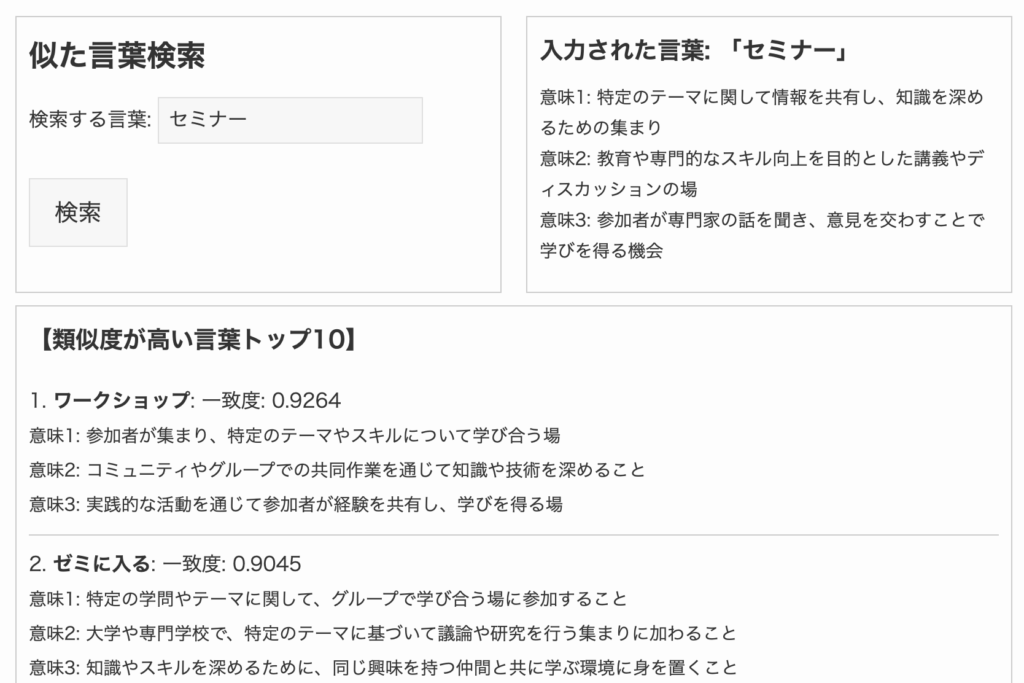本記事では、つるむの言い換え語・同義語(類義語)を解説します。
- ビジネスで使えるきっちりした類語
- 友達同士でカジュアルで使える類語
に分けていくつかのアイデアをまとめました。
また、カタカナ・英語でかっこよく言い換えたい場合のワードもいくつか紹介します。
実際に使われているワードばかりです。ぜひ参考にしてください。
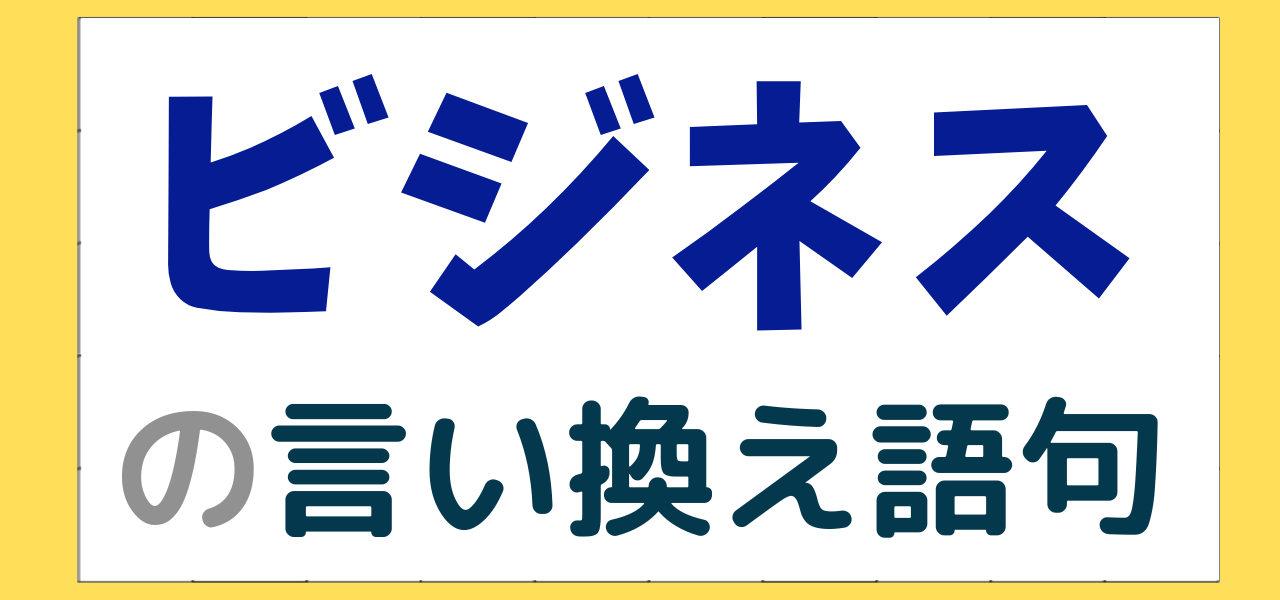 →ビジネスの言い換えを見る | 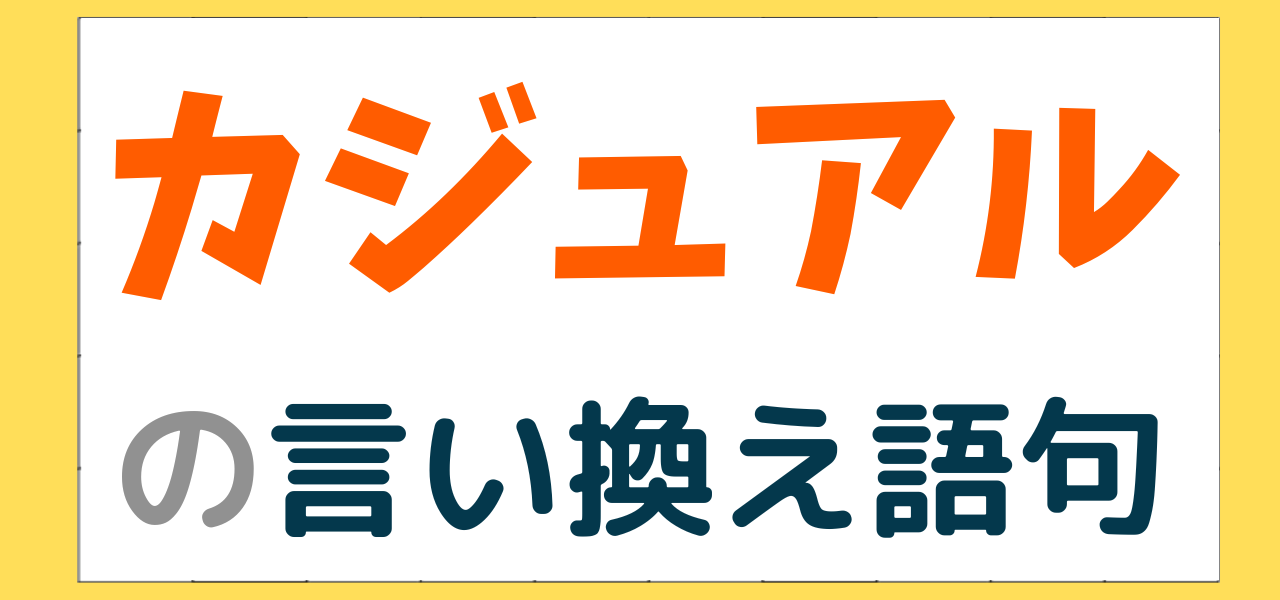 →カジュアルの言い換えを見る | 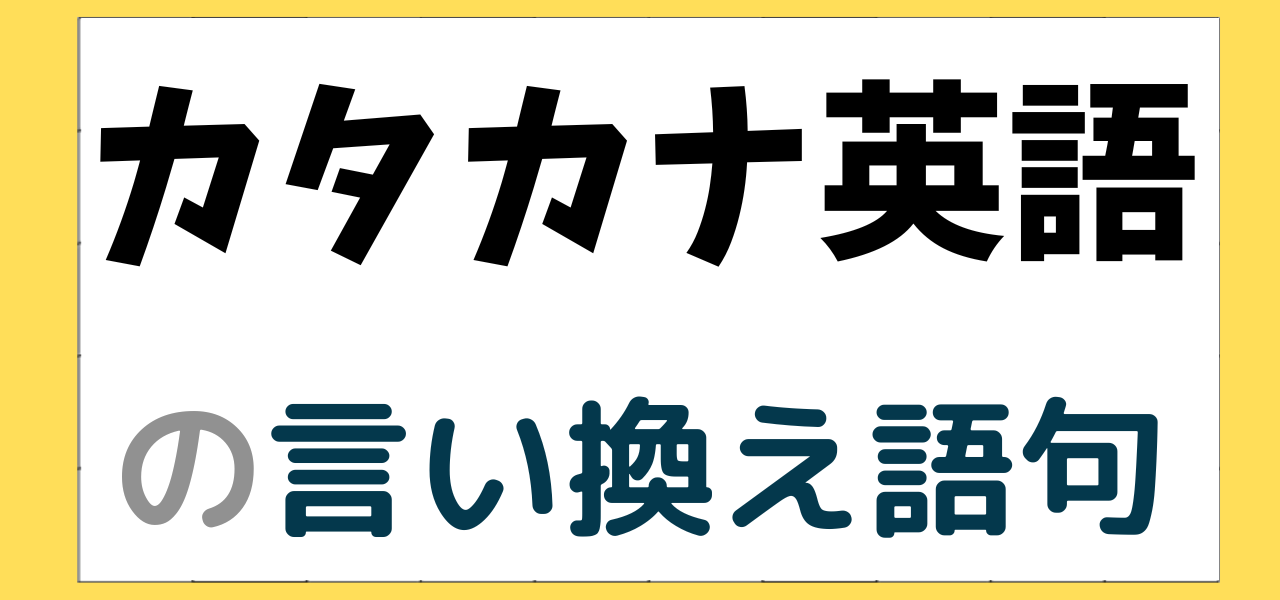 →英語・カタカナの言い換えを見る |
つるむとは? そもそもどんな意味か?
まずはつるむとはどんな意味なのかをおさらいします。
すでに意味をご存知の方は、次の項目まで飛ばしていただき大丈夫です。
意味
まず意味は以下のとおりです。
—
仲間やグループと共に行動すること—
特定の人々と親密な関係を築くこと意味を全て見る
- 集団での活動や協力を重視すること
- 人との関係を深めること
例文
つづいて、つるむを用いた例文を紹介します。
彼はいつも友人たちとつるんで遊んでいる。
仕事の合間に同僚とつるむことが多い。
例文を全て見る
- 彼女は仲間たちとつるんで新しいプロジェクトを進めている。
- 週末は友人とつるんでハイキングに出かける予定だ。
- 彼はいつも同じグループとつるんで行動する。
注意点(違和感のある、または失礼な使い方)
この言葉を使ううえでの注意点は以下のとおりです。違和感のある使い方にならぬよう注意しましょう。
—
この表現は、友情や仲間意識を強調しますが、他者との関係において依存的なニュアンスを持つこともあるため、注意が必要です。ビジネスで使える丁寧なつるむの言い換え語のおすすめ
ビジネスで使えるフォーマルな言い換え語を紹介します。
それぞれ見ていきます。
チームを形成する
まずは、チームを形成するです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
ネットワーキング
2つ目は、ネットワーキングです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
協力関係を築く
3つ目は、協力関係を築くです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
パートナーシップ
4つ目は、パートナーシップです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
コミュニティを形成する
5つ目は、コミュニティを形成するです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
連携を強化する
6つ目は、連携を強化するです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
関係を深化させる
7つ目は、関係を深化させるです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
協働する
8つ目は、協働するです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
結束を高める
9つ目は、結束を高めるです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
関係を構築する
10個目は関係を構築するです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
つるむのカジュアルな言い換え語のおすすめ
友達同士で使えるようなカジュアルな言い換え語のおすすめを紹介します。
仲間と遊ぶ
まずは、仲間と遊ぶです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
グループで過ごす
カジュアルの2つ目は、グループで過ごすです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
友達と集まる
つづいて、友達と集まるです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
遊び仲間
4つ目は、遊び仲間です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
フレンドリーな関係
5つ目は、フレンドリーな関係です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
みんなでワイワイ
6つ目は、みんなでワイワイです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
おしゃべり仲間
7つ目は、おしゃべり仲間です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
一緒に遊ぶ
8つ目は、一緒に遊ぶです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
仲良しグループ
9つ目は、仲良しグループです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
集まって騒ぐ
10個目は、集まって騒ぐです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
つるむの横文字・カタカナ英語の言い換え語のおすすめ
最後は横文字・カタカナ英語での言い換え語を紹介します。
こちらはリストのみとなります。
- コネクション
- ネットワーク
- グループ
- Hang out(遊ぶ)
- Socialize(社交する)
- Gather(集まる)
かっこよく表現したい際、参考にしてください。
まとめ
以上がつるむの言い換え語のおすすめでした。
さまざまな言葉があることがわかりますね。
基本的な意味は同じでも微妙にニュアンスが違ったりもするため、TPOに合わせて言い換え語を使い分けていきましょう。
振り返り用リンク↓